段位認定試験「かけ暗算」の問題例
被乗数(かけられる数)と
乗数(かける数)合わせて5~7桁の問題となります。
問題は最後の方に行くにつれて難しくなっています。
これが60問で制限時間3分です。
1問5点で全問正解すると300点、
290点取れば十段です。
段位認定試験「かけ暗算」の計算について
暗算科目なので、当然ですが、
そろばんは使ってはいけませんよ(笑)
制限時間は3分です。
非常に短いですよね!
それはもうあっという間です。
そのうちに、
60問の問題を解かなければなりません。
もうゆっくり計算している暇なんてないです。
段位認定試験「かけ暗算」の問題改正
実はこの段位の問題ですが、
私が現役の時から問題構成が改正されています。
私が現役の時は、
「かけ暗算」の問題はすべて“3桁×3桁”の問題でした。
今の問題は、
最初は“2桁×3桁”から入って、
最後の方は“3桁×4桁”となっていますね。
これは、
昔の問題に慣れている人にとっては、
非常に厄介な問題です。
この改正があった時の受験生も、
同じ感想を持ったのではないでしょうか?
“3桁×3桁”であれば、答えは5桁or6桁ですが、
“3桁×4桁”だと、答えは6桁or7桁になります。
暗算ができる限界が6桁までの人だったら、
“計算できない”または“時間がかかる”
ということになってしまいます。
つまり、
頭の中のそろばんが、
6桁の長さまでしかない人は、
“珠が入らない”ということになります。
しかも十段合格ラインは、
280点⇒290点に上がっています。
人によっては、
“難しくなった”と感じるのではないでしょうか。
段位認定試験「かけ暗算」の計算方法
私の場合、「かけ暗算」については、
被乗数の“あたま”から計算していきます。
“5×7”⇒“5×4”⇒“5×8”
“2×7”⇒“2×4”⇒“2×8”
という流れになりますね。
段位認定試験「かけ暗算」を早く解くためにしたこと
答えを記入しながら計算する
これはみんなやっている…というか、
3分で60問全部解くには、
これをしないと間に合わないです。
最初の問題だけ1~2秒で解いて、
あとは答えを記入しながら問題を見ます。
そして答えを書き終わる頃には、
次の問題を計算し終わっている状態にするんですね。
なので、
端から見ていると、計算しないで、
答えをずっと書き続けているように見えます(笑)
字は小さく書く
基本中の基本ですね。
他の記事にも書いたように、
読める範囲で字を小さく書いて、
動作を極力抑えるようにしましょう。
最初の簡単な問題に時間をかけない
これは、
問題が改正されたことによるものですが、
最初の方の問題は比較的簡単です。
その簡単な問題を、極力早めに解いて、
最後の方に出てくる問題の計算時間にあてましょう。
特にラスト10問ですね。
昔のようにすべての問題が、
同じ難易度ではないので、
そうやって工夫していきましょう!
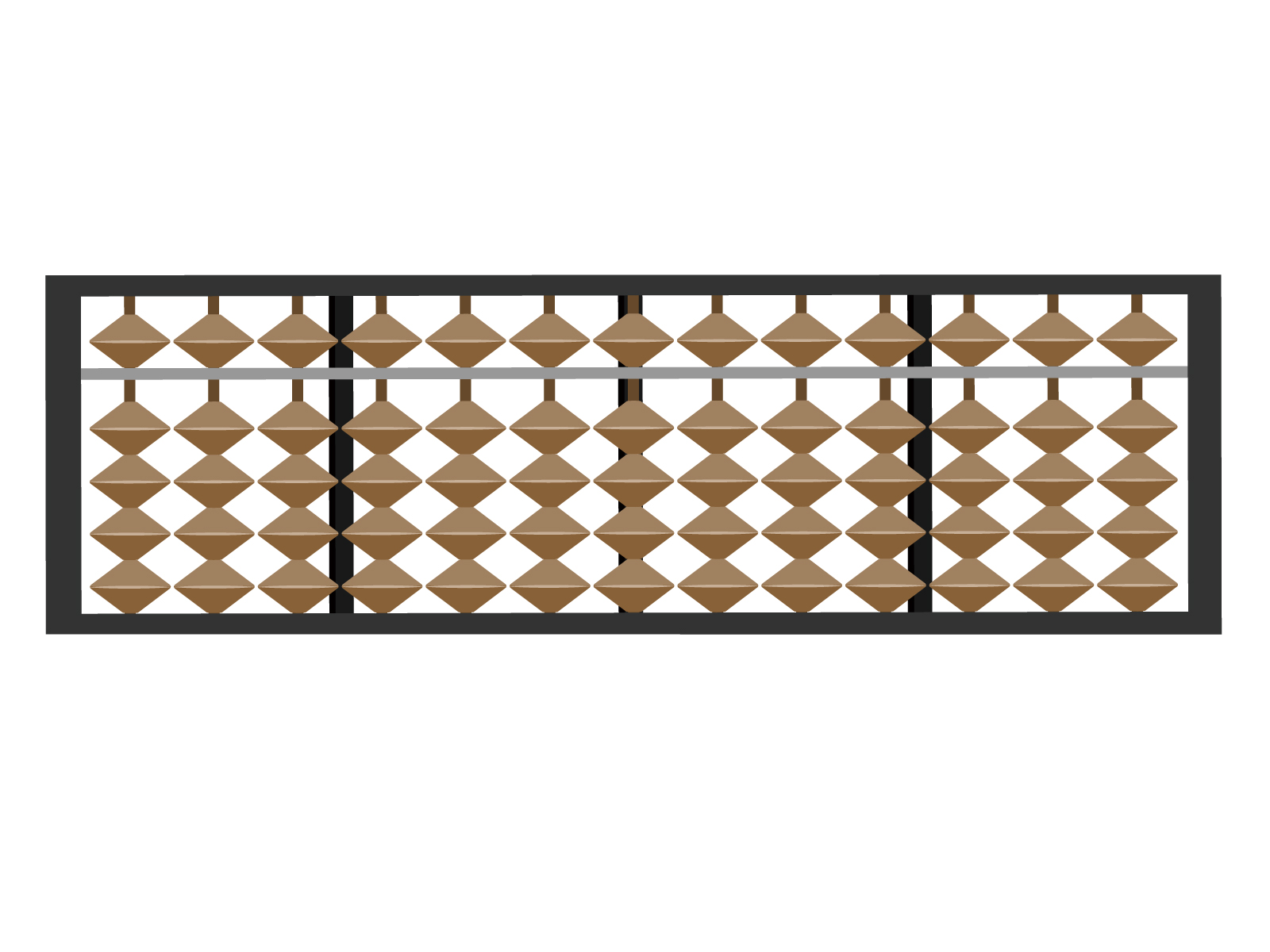
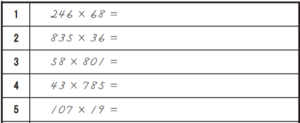
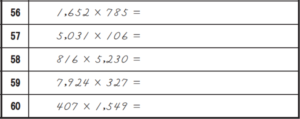

コメント